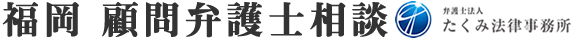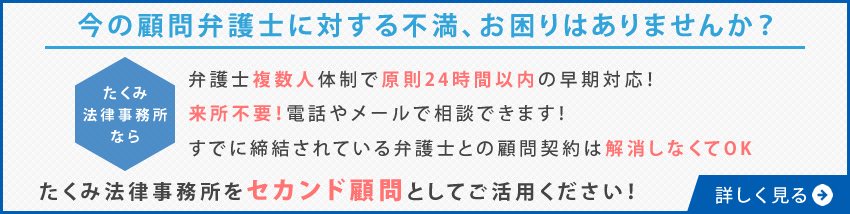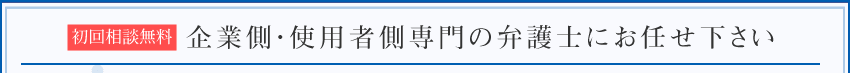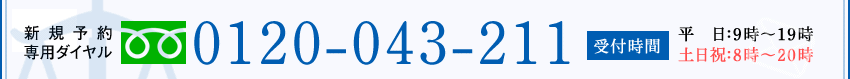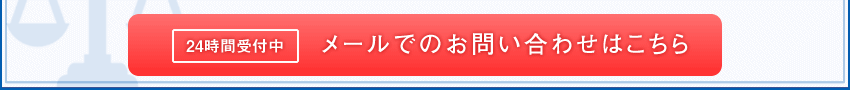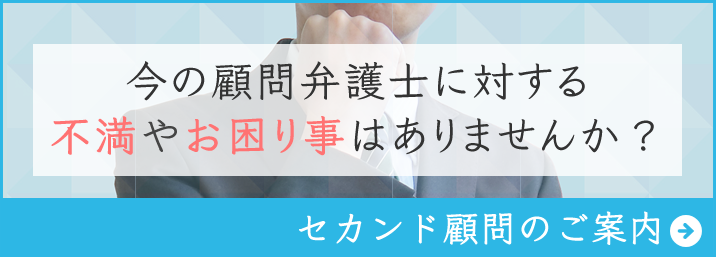学歴詐称や職歴詐称などの経歴詐称を理由に従業員を懲戒解雇できる?
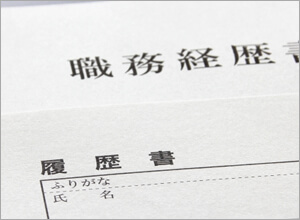
会社が労働者を採用する際、履歴書に書かれた最終学歴や職歴を参考にして決定することが多いと思います。
しかし、もしその経歴が実は詐称されていたら…?
「経歴を信用して雇用したのだから、辞めてもらわないと困る」と考える経営者の方も多いのではないでしょうか。
今回は、経歴詐称を理由とした懲戒解雇が法的に認められるのか解説いたします。
そもそも「懲戒解雇」とは
懲戒解雇は「懲戒処分」の一種です。
懲戒処分とは、会社の規律に反した労働者に対する「制裁」を指します。
会社が労働者に対して一方的な制裁を課すためには、就業規則において懲戒の種類と該当事由を定め、労働者とあらかじめ合意をしておく必要があります。
多くの企業では、就業規則等に「労働契約時に、最終学歴や職歴等、重大な経歴を偽り、会社の判断を誤らせたものは、懲戒解雇とする」という内容の規定を設けていると思います。
経歴詐称を理由に従業員を懲戒解雇するためには、就業規則等にこのような規定があることが前提となります。
どのような経歴詐称が懲戒解雇事由になるの?
就業規則に上記のような規定があったとしても、全ての経歴詐称が懲戒解雇事由になるわけではありません。
では、どのような経歴詐称が懲戒解雇事由に該当するのでしょうか。
この点について、裁判所は次のような判断をしました。
その経歴詐称が契約前に発覚していたとしたら、会社が労働契約を締結していなかったと認められる場合、もしくは、少なくとも同一条件で契約を締結しなかったと考えられる場合には、「重大な経歴の詐称」に当たり、懲戒解雇ができる。
つまり、契約を締結する決め手となった重大な経歴を偽った場合には、懲戒解雇が可能になるのです。
労働者は経歴について答える必要があるの?

労働者には、最終学歴や職歴について会社から質問された場合には答える義務があるとした裁判例があります。
最終学歴や職歴というものは、その労働者の労働力の評価に直接関わる事項でありますし、職場への適応性、貢献意欲、企業の信用の保持といった企業秩序の維持に関係する事項でもあるからです。
ですので、会社が必要な範囲内でこれらの経歴について申告を求めた場合には、労働者は真実の経歴を伝える義務を負うのです。
他方、犯罪歴は個人情報保護法で「要配慮個人情報」とされており、会社があらかじめ本人の同意を得ないで情報を取得することが禁止されています。
経歴詐称の具体例
では、経歴詐称の種類別に具体的に検討してみましょう。
最終学歴
高卒であるにもかかわらず大卒と偽るような最終学歴の詐称は、重大な経歴詐称に当たります。
その労働者の労働能力について会社の評価を誤らせ、本来であれば結ぶはずではなかった雇用契約を締結してしまったり、本来与えられるはずのない高い初任給や全く別の人事コースが用意されるなど、その後の労務管理にも支障をきたすからです。
したがって、この場合には企業秩序に関する事項の申告義務違反として懲戒解雇の対象となります。
ただし、会社が採用するにあたって学歴不問としていた場合など、学歴が労働力の評価に影響がない場合には解雇が認められない場合もあります。
職歴
職歴の詐称も重大な経歴詐称として懲戒解雇事由になりやすいです。
職歴は労働者を採用するかどうかの決定的な動機になることが多く、労働契約の締結において非常に重要な事項であるといえるからです。
特に、専門性の高い職歴を詐称されたことで労働契約の締結をした場合や、職歴を有しているゆえに高額な賃金の支払いや重要な職種を与えている等の事情があれば、「重大な経歴の詐称」にあたり懲戒解雇事由になります。
過去の裁判例には、ソフトウェアの研究開発や制作を行う会社において、JAVA言語のプログラミング能力が職務に必要であった場合に、その能力がほとんどなかったにもかかわらず、その能力があると思わせる嘘の職歴を記載し、面接でも同じ内容のことを説明して採用された事案でには、経歴詐称を理由に懲戒解雇とすることは有効であるとしたものがあります。
もっとも、学歴詐称の場合と同様に、職歴が労働力の評価に影響がない場合には解雇が認められない場合もあります。
犯罪歴
すでのご説明したとおり、犯罪歴は本人の同意を得ないで情報を取得することが禁止されています。
また、犯罪歴は労働者の労働能力と直接関係しない場合が多く、労務管理や企業秩序の維持に影響があるといえるかの判断は難しい部分があります。
したがって犯罪歴については、最終学歴や職歴の詐称とは異なる特別な配慮が必要とされます。
最後に
いかがだったしょうか。
経歴詐称があるからといって必ずしも懲戒解雇にできるとは限らず、使用者は難しい判断を迫られる場合があるということをご理解いただけたかと思います。
不用意に解雇をすると、労働者側から不当解雇として争われ、大きなトラブルにつながる可能性がありますので慎重な判断が必要です。
対応に困った場合には、弁護士に相談ください。
個別の事情について検討し、会社が取りうる最善の策をご提案いたします。