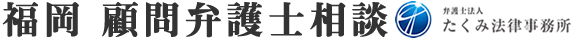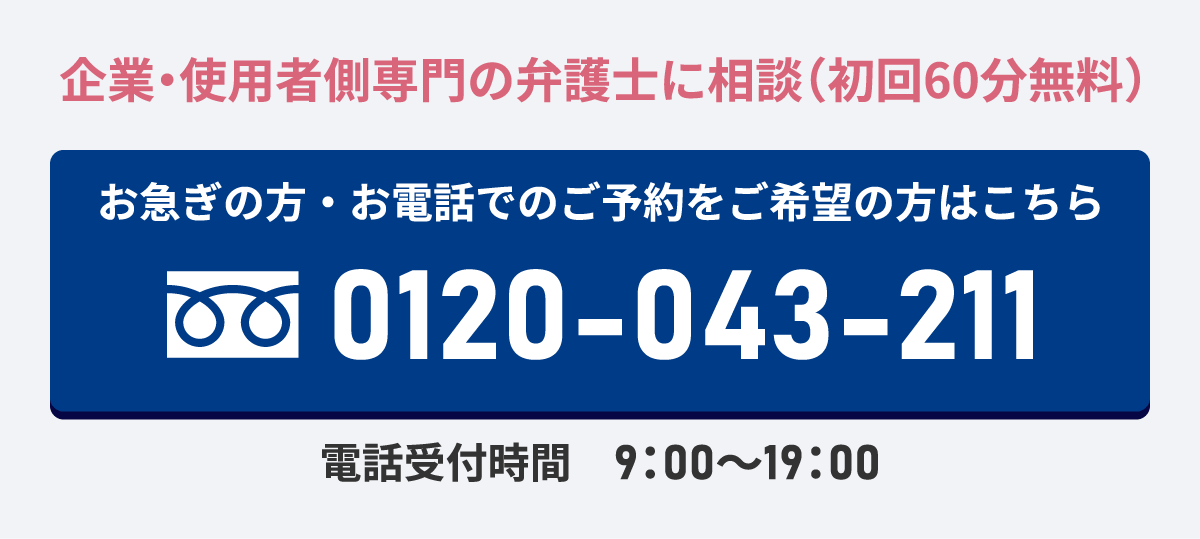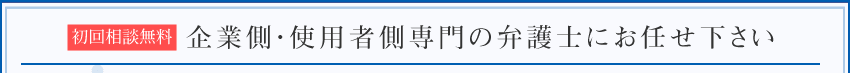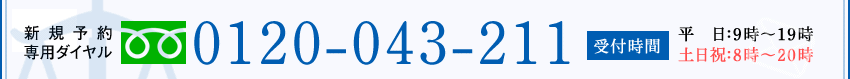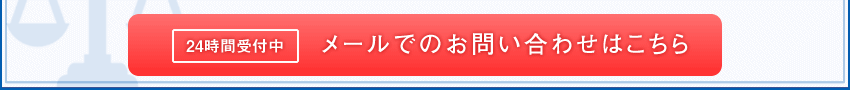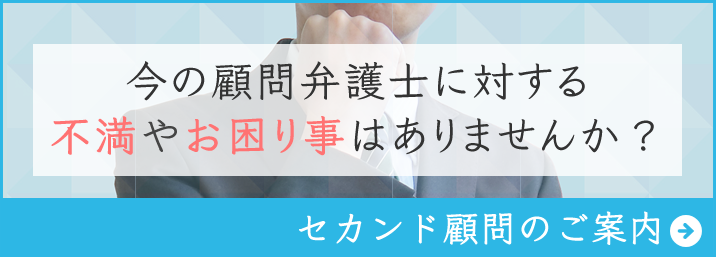はじめに

企業からの相談で頻繁に寄せられるのが、「従業員から労働審判を申し立てられたが、どのように対応すればよいのか」というご質問です。
労働審判制度は、2006年(平成18年)に施行された比較的新しい紛争解決手続であり、原則として3回以内の期日で結論が出されるため、企業にとっては極めて短期間での対応が求められます。
申立てを受けてから初回期日までの間に十分な準備ができるかどうかが、結果に影響を及ぼす可能性があります。
本記事では、労働審判制度の基本的な仕組みに加え、管轄のルール(どの裁判所で手続が行われるのか)と取り扱い可能な事件の範囲について、企業の経営者・人事担当者の方に向けて解説します。
なお、本記事の内容は2026年2月時点の法令に基づいています。
労働審判制度
労働審判制度は、労働審判法(平成16年法律第45号)に基づく紛争解決手続です。
「個別労働関係の民事紛争」、すなわち個々の労働者と事業主との間で生じた労働関係に関する民事紛争を、迅速かつ適正に解決することを目的としています(労働審判法1条)。
この制度の大きな特徴は、以下の点にあります。
迅速な解決
原則として3回以内の期日で審理が終結します(同法15条2項)。
平均審理期間は約2.5〜3ヶ月とされており、通常の訴訟と比較して大幅に短い期間で結論に至ります。
専門性のある審理
裁判官1名と、労働関係に関する専門的な知識・経験を有する労働審判員2名の合計3名で構成される労働審判委員会が審理します。
柔軟な解決
まず調停(話し合いによる解決)を試み、調停が成立しない場合には労働審判(判断)が下されます。
近年の新受件数は年間3,000〜4,000件程度で推移しており、約70〜80%の事件が調停成立または審判によって解決に至っているとされています(司法統計年報(民事・行政編))。
労働審判の管轄
労働審判を申し立てられた場合、まず確認すべきなのが「どの裁判所で手続が行われるのか」という管轄の問題です。

土地管轄
労働審判法2条1項は、労働審判事件の土地管轄について、以下の3つの地方裁判所を定めています。
-
相手方の住所地等を管轄する地方裁判所:
条文上は「相手方の住所、居所、営業所もしくは事務所の所在地」を管轄する地方裁判所とされています。企業が相手方となる場合、本店所在地だけでなく、営業所や事務所の所在地を管轄する地方裁判所も含まれます。
-
労務提供地を管轄する地方裁判所:
労働者が現に就業している、または最後に就業していた事業主の事業所の所在地を管轄する地方裁判所にも管轄が認められます。
-
当事者が合意で定める地方裁判所(合意管轄):
当事者間の合意により管轄裁判所を定めることも可能です。この合意は書面でしなければなりません(労働審判規則3条)。
たとえば、本店が東京にある企業の大阪支店で勤務していた従業員が労働審判を申し立てる場合、東京地方裁判所(本店所在地)と大阪地方裁判所(労務提供地)のいずれにも申立てが可能ということになります。
合意管轄については、実務上、雇用契約書へあらかじめ管轄合意条項が定められているケースがあるものの、その有効性は個別の事案ごとに異なるため、留意が必要です。
もっとも、管轄合意条項を雇用契約書へ定めておくことは、紛争時の予見可能性を高める観点から検討に値します。
事物管轄
労働審判手続は地方裁判所の手続であり、簡易裁判所では取り扱われません。
請求額の多寡にかかわらず、地方裁判所に申し立てる必要があります。
なお、実務上、申立ては地方裁判所の本庁または一部の支部で受け付けられており、すべての支部で労働審判を扱っているわけではない点にも留意が必要です。
移送
労働審判法3条に基づき、裁判所は、事件を処理するために適当と認める場合には、労働審判事件を他の管轄裁判所に移送できます。
たとえば、証拠や関係者の所在地等を考慮して、別の地方裁判所で審理するほうが適切と判断される場合などが想定されます。
労働審判で取り扱える事件
対象となる事件(個別の労働関係民事紛争)
労働審判の対象となるのは、個々の労働者と事業主との間における労働関係に関する民事紛争です。具体的には、以下のような事件が典型例として挙げられます。
解雇・雇止めの効力に関する紛争
普通解雇、整理解雇、懲戒解雇の有効性、有期雇用契約の更新拒否など。労働審判でもっとも多い類型とされています。
未払い賃金・残業代の請求
時間外労働、休日労働、深夜労働に対する割増賃金の未払いなど。
退職金の請求
退職金の不支給や減額に関する紛争。
ハラスメントに基づく損害賠償請求
パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントを理由とする損害賠償請求。
配転命令の効力に関する紛争
転勤や配置転換の命令が権利濫用に当たるかどうかが争われるケースなど。
対象とならない事件
一方で、以下のような紛争は労働審判の対象とはなりません。
集団的労使紛争
労働組合と使用者との間の紛争(団体交渉の拒否、争議行為に関する紛争等)は、「個別」労働関係民事紛争には該当しないため、労働審判の対象外です。
これらの紛争は、労働委員会における不当労働行為の審査等、別の手続で扱われます。
公務員の勤務関係紛争
国家公務員や地方公務員の勤務条件に関する紛争は、国家公務員法や地方公務員法等の特別法が適用されるため、労働審判の対象とはなりません。
労働者性が認められない場合の紛争
業務委託契約やフリーランスとして働く方の紛争については、当該契約関係における「労働者性」が認められなければ、労働審判を利用できません。労働者性の判断は個別の事情に基づいて行われるため、微妙なケースについては専門家への相談が推奨されます。
24条終了 — 労働審判が打ち切られるケース
労働審判法24条は、労働審判委員会が「事案の性質に照らし、労働審判手続を行うことが紛争の迅速かつ適正な解決のために適当でないと認めるとき」に、労働審判事件を終了させることができると定めています。これを実務上「24条終了」と呼んでいます。
24条終了が行われる典型的な場面としては、以下のようなケースが挙げられます。
- 事実関係が複雑で、3回の期日では十分な審理が困難な場合
- 多数の証人尋問が必要となる場合
- 当事者間の事実認識に大きな隔たりがあり、調停による解決の見込みがない場合
24条終了がなされた場合、労働審判手続の申立ての時に訴えの提起があったものとみなされ、通常の訴訟手続に移行します。
そのため、企業としては、労働審判で終結しない可能性も念頭に置きながら対応を検討することが重要です。
企業が労働審判を申し立てられた場合の初動対応
労働審判において、企業側の対応でもっとも重要なのは初動の迅速さです。
労働審判は原則3回以内の期日で終結するため、第1回期日が審理全体の方向性に大きく影響するとされています。
そのため、申立書を受領した段階から、以下の対応を速やかに進める必要があります。
-
答弁書の準備:
申立書の内容を精査し、企業側の主張・反論を整理した答弁書を作成します。
答弁書の提出期限は第1回期日の前に設定されますので、限られた期間内での準備が求められます。
-
証拠の整理:
雇用契約書、就業規則、賃金台帳、勤怠記録、メールのやり取り、面談記録など、関連する証拠を漏れなく収集・整理します。
-
第1回期日への備え:
第1回期日では、労働審判委員会から直接質問を受けることがあります。
事実関係を十分に把握したうえで臨むことが不可欠です。
-
弁護士への早期相談:
労働審判の手続は迅速に進行するため、申立書を受領した段階で速やかに弁護士に相談し、対応方針を決定することが重要です。
最後に

労働審判は、企業にとって短期間での対応を迫られる手続です。
初動対応の遅れは、企業にとって不利な結果につながるおそれがあります。
特に、管轄や対象事件の範囲といった制度の基本的な枠組みを理解しておくことは、適切に対応するための第一歩です。
労働審判を申し立てられた場合は、できるだけ早い段階で労働問題に詳しい弁護士へ相談し、適切な対応を進めていくことが推奨されます。
当事務所では、労働審判への対応に関するご相談を承っております。ご相談をご希望の方は、お問い合わせください。
お問い合わせはこちら